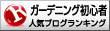注目の投稿
こんにちは。
鉢上げするときのポイントとしては、
根っこの様子です。
今日は、ブドウの挿し枝の鉢あげを行いました。
鉢上げするときのポイントとしては、
1.ブドウは過湿を嫌うため、水はけの良い土を使用する。
2.根が出てから行う。植え替え時もできるだけ、いじらずに行う。
3.種から育てるより、挿し枝の場合は大きくなるスピードが速い。
に注意して行いました。
今日のブドウの様子です。
左の鉢植えが挿し枝を取った元の株(2年目)、右が今日の主役の挿し枝のブドウです。
1つの芽から2,3葉出ています。
挿し枝(植え替え)行ったのは1月8日なので、ちょうど今日で3カ月になります。
本体の植え替えの時に切落した、株上部の枝部分です。
約20cmの長さで3本取れました。
捨てられなくて、挿し枝にしました。
 |
| 左:3月24日、 右:4月8日 |
3月24日には全く見えなかった根が、今日見るとしっかり出ています。
鉢上げでよく問題になるのが「ちゃんと根っこが出ているのか?」ということです。
透明プラコップなら根が張っているか見えるので、便利です。
今回使用する材料です。
・鉢底石(鉢の底用)
・赤玉(小粒)
・バーミキュライト
・緩効性肥料マグファンプK
・鉢底用アミ ※左下の黒い丸いもの
植木鉢は6号を2個、5号を1個使用しています。
支柱を2本ずつセットしています。
※支柱の名前がわかりません。直径2mmの緑色のビニール被覆された針金みたいなものです。
鉢の底に何かさせそうな場所があるのが、以前から気になっていました。
こうやって使うのかはわかりませんが、支柱の足を差し込んでいます。
土に挿すだけだと最初のうちは動いてしまいますが、動かないのでこの使い方を気に入っています。
土が出ないように、底に鉢底用の網をおきます。
今回鉢底に使用したその名も「鉢底石」です。
植え替えをしようと思って、家にある資材を確認したら、鉢底にいつも使用している赤玉(大粒)がありませんでした。そこでホームセンターに買いに行ったのですが、行ったお店には大袋の赤玉(大粒)はあるのですが、5L程度の小袋では置いていませんでした。
そこで急遽買ったものです。
発泡性の石のようで、とても軽いです。
軽量で衛生的、通気性と排水性に優れていると説明書きがあります。
粒はこんな感じです。
これを鉢の底のネットが隠れる位入れます。
そのうえに、3mmのふるいを通した赤土(小粒)を、隠れる程度入れます。
ふるいを通して、通気性を邪魔する細かく砕けた土を取り除いています。
その上に、一株当たり小さじ1杯分のマグファンプKを元肥えとして入れます。
真ん中に植えるので、鉢のきわに入れています。
今度は、ふるいを通した赤玉とバーミキュライトを混合した土を入れます。
赤玉とバーミキュライトの混合比率は、赤:バ=2:1程度です。
ブドウは過湿を嫌うため、水はけがよい土にするために赤玉を多めにしています。
これを肥料が隠れる程度に入れます。
植え替える挿し枝をプラコップから出しました。
ちゃんと根が張っています。 ※透明なので見えてました。
3本のうち、2本は根があるのがすぐわかりましたが、1本は深さが深かったのか、一見すると出ていないように見えました。
 |
| 一見すると根がないですが、よく見ると出始めています。 |
でも、よく見るとちゃんと根が出始めています。
これなら大丈夫でしょう。
なるべく土を落とさないようにして、鉢の真ん中に置きます。
倒れないように手で支えながら上まで土を入れます。
土は、赤:バ=2:1の方です。
鉢の上数cmをウォータースペースとして残して、土を入れたところです。
元々挿してあった札はこの株に付けました。
他の枝も、同じように植え付けます。
植え付け後、このようになりました。
今回、6号鉢を使用したのは、昨年種から芽が出た親株が、一年目で5号鉢いっぱいに根がまわり切るくらい成長したからです。
タネから始めるよりも、挿し枝の方が成長が早いです。
そのため、少なくとも5号より大きい鉢を使用する必要があると思ったからです。
最後に、鉢の底からジャージャーと出る位にたっぷり水を水やりを行いました。
鉢から出る水は、最初赤土の茶色い水が出てきますが、透明になるまで流します。
これで、赤土の粉を洗い流します。
次の作業としては、1節から2つ以上の芽がある部分を、1つにすることです。
近いうちにやりたいと思います。
今日の作業はここまでです。
関連記事:
ここまで読んでいただきありがとうございました。
ガーデニング初心者ランキング